カタログ研究シリーズが好評だったのでTAMAに手をつけたのですが…
ありがたいことにTAMAさんはカタログ全てデータベース化してくださっている!!
…ということで、TAMAさんの歴史そのものに手を突っ込むことになってしまいました笑
まさかの長編になりますがご勘弁ください…!
ブランド名は初代社長の奥さんの名前
| 1962年 | 星野楽器が自社の楽器工場「多満製作所」を立ち上げる。これがブランド名の由来。 |
| 1966年 | Star名義でドラム生産開始。 |
| 1974年 | TAMAというブランドで世界進出を目指す。 |
TAMAというブランド名の由来は星野楽器 初代社長である星野義太郎の妻「星野多満」の名前だそうです。
多満さんは会社の経理全般を取り仕切り、星野楽器の創業期から戦前までの経営の重要な役割を担っていました。ドラム工場の開業に当たってはその名を「多満製作所」、ブランド創設時には「TAMA」と、いずれも彼女の名を冠し敬意と発展を誓ったそうです。
TAMAの誕生時はハードロックの流行に着目していた
TAMAさんのホームページには次のように書かれています。
1960年代~70年代にかけてハードロックが世界的に流行。ドラムは音量を要求され、大口径化、多点キット化が進む。その中で市場ディマンド(※「要求」のこと)は安定してしっかりセッティングできるHW(ハードウェア)だった。
そこでTAMAブランドはハードウェアの機構から独自性を追求することで地盤固めに取り掛かる。ナイロンブッシュ、ブームシンバルスタンドなどがその典型的な例と言える。
ドラム部門においては、1970年代後半に発売されたSuperstarがドラムメーカーとしての転換点となる。Billy Cobhamなど世界のトップアーティストとの契約が後押しとなり、世界的な認知を獲得していった。
当時、ジャズ界ではマイルスデイビスやコルトレーンが活躍し、モードジャズやファンキージャズ、ボサノバといった新しい風が吹いていました。ですが、記述から察するに、TAMAは初めからロックに照準を合わせていたことが伺えます。
1960年代はローヤルスターシリーズとスターシリーズが主力

1967年のものだけカタログデータが残っていました。当時、star名義での製品は「ローヤルスターシリーズ」と「スターシリーズ」。1967年当時はシンバルも手がけており、「ローヤルスターシンバル」「スターシンバル」がラインナップされていました。
1970年代からラインナップが加速!インペリアルスター等が誕生!
1974年、TAMA名義になってからカタログが増加しており、TAMAの躍進がどんどん見て取れるようになります。
1974年、TAMAの活動本格始動!
1974年のカタログでTAMA名義での活動がスタートします。ラインナップは以下です。
- サターン12+1
- ステージマスターシリーズ
- キングビートシリーズ
- マルス
- マーキュリーシリーズ
- スイングスターシリーズ
「サターン12+1」はなんと12点セット+スネアの超多点2バスキット!!
この頃にはスネアドラムもラインナップされるようになり、キングシリーズなど、木胴とメタル胴の両シリーズが並びました。材料については詳細が明記されていません。
1976年、スーパースターシリーズ、インペリアルスター登場!
1976年のカタログ概要は以下です。
- スーパースターシリーズが登場
- インペリアルスター登場
- ハードウェアのラインナップが充実
その他の点としては、スネアドラムにもインペリアルスターが登場している点があります。以下がスネアドラムのラインナップです。
| インペリアルスター | 金属胴(詳細不明) |
| スーパースター | 木胴(4プライ、ウッドシェル) |
| ロイヤルスター | 金属胴(詳細不明) |
スーパースターシリーズが登場
1976年のカタログではスーパースターシリーズが登場!この時のスーパースターシリーズのバスドラムサイズは基本深さが15インチ。これもパワーを求めた結果だと思われます。
当時のカタログからは、TAMAがアクリルやファイバー樹脂ではなく木による質の高いパワフルなサウンドにこだわっていた様子が伺えます。バスドラムのフープをウッドフープに変えたのもこの時期のようです。
インペリアルスター登場
インペリアルスターも1976年のカタログに登場(HPでは1974年発表となっている)!木胴に特殊コーティング材を塗装した材を使用していたそうです。当時は「スーパーコンプレスシェル」という製法をとっていました(詳細不明)。
当時からラグにもこだわっており、「スプリングを入れないダイキャスト製のタマオリジナル方式」を採用。レッグにもこだわっており、ゴムとスパイクの切り替えがバスドラムだけでなくフロアタムでもできるようになっています。
ハードウェアのラインナップが充実

この頃からハードウェアが充実し始めます。「ステージマスター」「ステージキング」「ステージスター」「ハイエース」「ステージエース」「バンドエース」という多種類のハードウェアがラインナップされています。
1976年のカタログではハードウェアの堅牢さもアピール。ダブルレッグを取り入れたことが記載され始めたのもこの頃です。ドラムペダルについてもバネの耐久性をアピールしています。
1977年、ファイバースターも登場!
1977年のカタログ概要は以下です。
- スーパースターの材がバーチと明記
- インペリアルスターは特殊コーティングした木胴と明記
- ファイバースター登場
- ナイロンブッシュ登場
その他の点は、1977年カタログにてニューキングビートドラムペダルが登場し、すでにビーター角度がフットボードの角度と独立して調整できることをうたっていることがあります。
また、この頃はどの商品についても「耐久性」が多くうたわれています。当時は業界の中で故障の問題が大きかったのだろうと推察されます。
他にも、当時のヘッドやシンバルのチョイスが明記されていたので以下で紹介します。
| ヘッドのメーカー | 国 |
|---|---|
| CANA-SONIC | アメリカ |
| TAMA | 生産はアメリカ |
| EVER PLAY EXTRA | イギリス |
| RS200 | アメリカ、日本と表記されている |
| シンバルのメーカー | 国 |
|---|---|
| ジルジャン | 明記なし |
| ザンキ | イタリア |
| ロメン | ドイツ |
| スイングスター | 日本 |
スーパースターの材がバーチと明記

1977年カタログから一部にドラムの材が明記され始めます。スーパースター(9500、9600)をリリースし、材はバーチと書かれています。
ヘッドは「CANA-SONIC」という会社の物が使われていました。スーパースターシリーズのスタンド類はアルミダイキャスト製で、軽量さと安定性を売りにしています。
インペリアルスターは特殊コーティングした木胴と明記
この時のインペリアルスターの材について「レインフォースメントのついた木胴に特殊コーティング材を塗装」と発表されています。湿気の影響を受けないヘビーで抜けの良いサウンドを売りにしていました。
他にもスイングスター、ロイヤルスターとラインナップがありますが、材について大きな違いは明確にはなっていませんでした。
ファイバースター登場
ファイバースターも登場します。ファイバーグラスシェルのパワフルな音と耐久性がポイントでした。
ファイバーグラスシェルとは樹脂とガラス繊維を混ぜ合わせて生成したもの。
樹脂とは、この場合はおそらく合成樹脂。石油などの科学由来の素材をもとに作られた素材。プラスチックもこの合成樹脂を加工して作ったもの。
ナイロンブッシュ登場
ハードウェアのナイロンブッシュについても言及(HPには1976年登場となっている)。このカタログからスタンド類やタムホルダーなど、ハードウェアにさくベージ数が増加。ナイロンブッシュについて多く言及。
ちなみにブームスタンドの発祥はTAMA!!
1979年、カタログのトップがハードウェアに!
カタログは1978年がなく、1979年に移ります。1979年のカタログはハードウェアの紹介がトップ!ハードウェアがヒットもしくはそこに注力している様子が伺えます。
その他にもカタログの情報が非常に充実しています。以下が概略です。
- ドラムの歴史について紹介
- ドラムの材について紹介
ちなみにこの頃ついに24インチの大口径バスドラムが登場します。また、当時はフロントヘッドを外してプレイする際にシェルが歪む可能性があったため、「サポーター」というパーツがあったようです。フープを固定したり、つっかえ棒のような物だったりするようなものでした。
スネアは「メタル胴」「特殊軽合金胴」「木胴」「バーチ胴」の4種類が紹介されています。フープはダイキャストフープとプレスフープがありました。ストレイナーはファーストアクション、イージーアクション、パラレルアクションの3種類が記載されていますが、それぞれの詳細は不明です。
ドラムの歴史について紹介
このカタログではドラムの歴史についても触れています。まずドラム自体の歴史について。
ドラム自体の歴史は紀元前3000年くらいのイラクに遡るが、ドラムセットという形になったのはつい最近。
ドラムのサイズがいかにして決まってきたかは、実はメーカーが木で完全な円柱を作るような高価な機材を投入できず、当時木製だったランプのかさを使ったことでサイズが決まった。
ランプのかさのサイズが12,13,14インチだったのでドラムも同様になったとのことです!音の研究の結果ではないんですね!驚きです。
ドラムの材について紹介
この頃のTAMAはベーシックなドラムの材として「メイプル」「バーチ」「ビーチ」「ガム」を紹介しています。ガムってこの頃すでにメジャーな素材だったんですね…!
スーパースターシリーズにてこの時初めて明確に材が表記され、バーチ材と書かれています。真円度の正確性やヘッドを外しても変形しない強靭さをアピールされていました。
インペリアルスターの8500シリーズに初めてマホガニーを使用したとのこと。また、プライ数については6プライが一般的としています。
ファイバースターではブラックファイバーグラスシェルを採用。耐久性の強さを強調されていました。ファイバーやアクリルシェルについて、詳細についても言及されています。
ファイバーは木よりも密度が高く固いため、音が胴自身からでなく表面から返って来る。このためパワフルで明るく、アクセントがつけやすい。
ファイバー胴は高速で回転する機械の中に樹脂を入れて作るため、一定の厚さで作れて真円度も抜群に良い。
アクリル胴については以下のように語られています。
アクリルはファイバーと木の中間の硬さ。ファイバーほどではないが明るくダイナミックな音が出せる。ショックに弱く壊れやすいデメリットもある。
メタルシェルについては次のように語れています。ただし、どのメタル材なのかは不明です。
メタルはどんな材よりも強く明るくパワフル。一定の鋭いエッジを持っていることも特徴。素早く大きな力で打った時に音がこもらないために硬いエッジが必要とされた。
TAMAの躍進はロックへの対応、堅牢さの追求が大きく関わる
ここまで調べてくると、TAMAさんの「THE STRONGEST NAME IN DRUMS」というテーマがとてもしっくりすることが分かります。当時は今では有り難く当たり前になっていますが、「強さ」がドラムに求められていたんですね。
…そして1970年代までで5000字のまとめw
おそらく3部作、20000字程度の大作になるかと思いますw
みなさん!なにとぞお付き合いを!笑




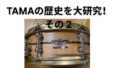
コメント