ありがたいことに以前Xにて、「サカエの研究もしてください!」というご依頼をいただきました。
そこで今回は、大変遅くなりましたが、サカエドラムの研究をしていきます!
ここでいつもならカタログ研究を行うのですが…、「サカエにはカタログがない…!!(厳密には薄めのリーフレットのみ)。
ですので、今回はネットの情報、実際にスネアを叩いてみた感想、そしてその他の資料を取り寄せて知った内容についてお話していきます。
サカエは100年前から続く会社!

サカエドラムはもともと「サカエリズム」という名前で会社をしていました。創業はなんと1925年!ちょうと100年前…!
サカエリズムさんは実質2000年代までヤマハのドラム部門を担当していました。経緯は1965年頃にさかのぼります。
当時、ヤマハさんはドラム制作のノウハウを持っていませんでした。当時は日本管楽器(ニッカン)という会社がドラムを作り始めていました。そのニッカンをヤマハが買収します。それによってヤマハの管楽器制作が始まるのですが、そのニッカンの中にドラム制作部門があったのです。
ヤマハがニッカンのドラムイズムを引き継ぎ、その中で、ニッカンと取引のあったサカエリズムとヤマハつながり、ヤマハがサカエリズムからドラム製作の技術を教えてもらうカタチでヤマハのドラム製作が始まったのです。
このようにして、サカエリズムとヤマハのコラボレートが始まっていきました。
「サカエドラム」は2010年頃に誕生

ヤマハとサカエのコラボレートは2008年頃に解消されます。ヤマハが別の工場やインドネシア工場を立ち上げたためです。そこでサカエは2009年、独自のブランド「サカエドラム」を立ち上げることになります。
サカエの製品は丁寧な作りが特徴的!
サカエドラムが立ち上がった当時は、さまざまなドラムのガレージメーカーが立ち上がっていた時期でもありました。その流れに乗っての会社設立ではないか、とも言われています。
ですが、それらのガレージメーカーとサカエドラムには大きな違いがあります。それは「サカエにはヤマハでのドラムづくりのノウハウが全て蓄積されている」ということ。
サカエドラムはヤマハのドラムづくりを一手に担っていたので、シェルづくりの釜も持っている上に、サンディングや塗装、エッジ加工まですべての技術があります。これらを存分に使い、集まった職人さんが丁寧にドラムづくりをしているののが、サカエドラムの大きな特徴です。
サカエはただの旧ヤマハのリイシューではない
実は、今回ヤマハの研究をするにあたり、昔私の大師匠から言われた言葉がとても印象に残っておりまして…
大師匠「サカエなんてあれやろ、要は昔のヤマハの音やんけ!w」
確かに一理ある…。実際ヤマハの名だたる名機、「レコーティングカスタム」「メイプルカスタム」といったものを作っていたのがサカエリズム。そうなってくると、その技術を使ったらその音になるやろ、と。
ただ、物作りにはすべて最初に「コンセプト」が存在します。サカエリズムはヤマハの掲げたコンセプトに基づいて良いものづくりをする、という立場だったわけです。これが、サカエドラムになったら「コンセプト」から自分で作ることになってくる。
言ったら、「本当はこうしたいのにな」「こうなったら良いのにな」と現場の職人さんが思っていたことを存分に詰め込んで制作したもの、それが現在のサカエドラムだと思うわけです。
- こだわった塗装
- こだわったパーツ製作
- 他のメーカーを意識した、ヤマハにはなかった新たな材の取扱い
この辺りにヤマハさんとの大きな違いを感じます。
サカエドラムの細やかなこだわりの解説
ここで、わずかに残っていた資料から、サカエドラムのこだわりが垣間見える情報をご紹介します。
ドラム製作には多くのミュージシャンからのフィードバックを重視
サカエドラムさんはドラムの製作にあたり、シェルの厚さ、素材、パーツの形状など、数百の組み合わせをテストしています。そうして制作したプロトタイプを多くのミュージシャンに試してもらい、そこから出た意見を存分に踏まえて改良を行っています。
その結果だと思いますが、サカエドラムさんにはエンドユーザーを意識した作りが多く見られます。
- マイティーヘイロ(内巻きフープ)の装備
- ミュートで対応しがちな余計な倍音を、そもそもフープの形状の工夫で整えておく
- ユニオンラグの装備
- ラグの連結部分の重さを調節することで音を引き締めておく
「みんな、こういうの使いやすいでしょ?」「こういうのが好きでしょ?」という作り手のねらいが見えてくる仕様がされている気がします。言葉選びが適切かはわかりませんがww
ドラムセットのパーツやエッジへのこだわりも強い
サカエドラムで有名なドラムセットが「Almighty」シリーズですね。こちらにはふんだんにサカエドラムさんのこだわりが詰め込まれています。
- エッジが厚くなっている
- シェルの振動を十分に伝達するため
- ラグ(トランスミットラグ)の採用
- 敢えて重量を持たせて振動(音)を効率的に伝える能力を高める

音の進行方向に物がある場合、音は「物にあたって跳ね返る成分」と「物を通過していく成分」に分かれるよ。そのとき、物が重いほうが、通過していく成分が少なく、より多くの音を跳ね返すよ。
サカエドラムのスネアを試奏
ここで、サカエドラムを3機種試奏した1000万円おじさんの感想をお伝えします。
次はサカエの研究について、動画で簡単に説明したものです。
あとがき:メーカー研究は楽しいけど、メーカーの音は分からない
これまでTAMA、CANOPUS、Pearl、そして今回のサカエとメーカー研究をしてきました。メーカーの研究をすると、各メーカがいろんなこだわり、熱意をもってドラムを作ってはるのが良くわかります。
一方で、動画内でもお話しましたが、「こういう材だからこういう音」ということが、本当に言いづらいもんなんだな、ということをとても実感しています。
いつもお世話になっているドラムショップAPOLLOの清水さんもおっしゃっていました。
「このメーカーだから、このシェルだからこう、ではなく、このスネアはこういう音、っていうふうに一台一台の音を楽しんでいったほうが良い。」
その通りだと思います。作りやパーツひとつひとつの音傾向は把握しておいたほうが良いですが、それらが組み合わさったときの音の方向性は無限大です。
一つの楽器との一期一会をしっかり楽しんでいる内に、もしかしたら色んな傾向についてつかめるときが来るかもしれませんね。



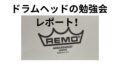

コメント